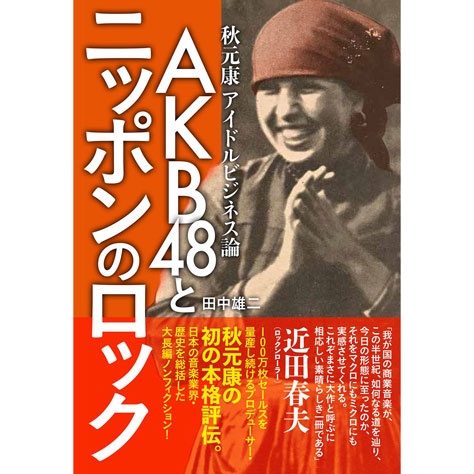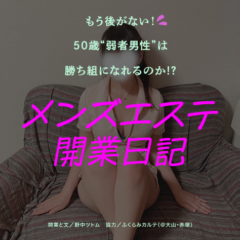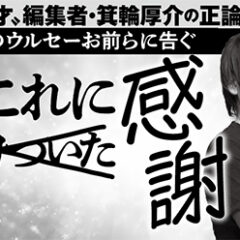111回 奇書 田中雄二『AKB48とニッポンのロック ~秋元康アイドルビジネス論』を読んで
この本を読みたいわけではなかったが、編集氏の依頼によってやらざるを得なくなってしまい、結果として多くの時間を費やしてしまった。本当に疲れた。
たぐいまれなる本だ。まず、700ページを超える分量に圧倒される。この本を書くために費やした時間や、このために資料にした量は莫大なものになるだろう。そこは素直に賛美の声を贈りたい。ここまで書いてきて、かつて難波弘之氏が著者・田中雄二氏の旧著『電子音楽イン・ジャパン』に対する指摘論文の冒頭で書いていた文章によく似ていることに気付いてしまった。引用させていただくと、「しかし、結論から述べてしまえば、志は高く、着目した題材もユニークであるし、資料点数も多く、新たな事実の発見や、いくつかの注目すべき指摘もあるが、問題点があまりに多いため、全編に渡って何か煮え切らない印象が残る著書である。」 。題材こそ変われど、印象としてはほぼ変わらない。引用部以外にも、両著に共通する問題を明確に指摘することになってる箇所が多いのだが、全文引用するわけにもいかないので、気になる方はリンク先を読んでいただきたい。さらに『電子音楽イン・ジャパン』に関していえば、言及範囲を手広くしすぎたため混乱しているとはいえ、著者が普段馴れ親しんでいるものについて言及しているわけだが、今回は著者が全く知識のないジャンルにも言及せざるを得なかったためか、記述や理解に雑な部分がいっそう目立っている。
タイトルに「ニッポンのロック」とあるが、実際に触れられているのは日本の音楽業界の歴史であり、また音楽業界の中でも著者が好んでいる界隈のことしか基本的に言及されていない。全体としては、自分の好きな業界と自分の好きな48グループを関連付けて語ろうとしている本なのであるが、その関連付ける作業が雑で強引な部分が多く見られ、思い込みではないかとしか言えない部分が続出する。
41pにおいて、日本のニューウェーブ文化と秋元康が近いところにあったという主張の根拠に、秋元作詞の『雨の西麻布』といとうせいこう作詞の『夜霧のハウスマヌカン』に同時代性や共通性があるという高木完氏(タイニーパンクス等)の発言を引用しているのだが、これはあまりに強引ではないだろうか。さらに秋元氏たちの溜まり場と、いとう氏たちの溜まり場が同じビルの別のフロアにあったということも根拠として語られているのだが、なぜ同じビルの別のフロアにいれば、文化的に近いところがあるのか理解に苦しむ。
東京のニューウェーブ~初期のHIPHOPシーンに関わる面子の中のテレビ業界に近い人たちと、業界人である秋元康の生活エリアが被っていたということや同時代性があったということは、両方とも同時代の業界の人だったということを表しているに過ぎない。論拠が雑である。
ことあるごとに著者は秋元康を80年代サブカルチャー、日本のニューウェーブやフォークに結びつけようとするのだが、その根拠は曖昧である。自分の好きなものとの関連性をかってに見いだして強引に結びつけようとしているように見える。秋元康は流行り物が好きなだけであって、たまたまそれが著者の趣味に合致する瞬間があるだけだというのが個人的な見解である。