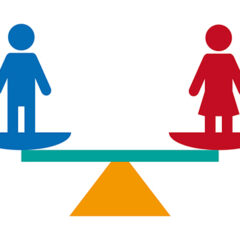2024年10月25日にダ・ヴィンチWebに掲載された「今の怪談ブームは危うい」実話怪談が今改めて脚光を浴びる理由【怪談師/作家・夜馬裕インタビュー】という記事がある。怪談師/作家の夜馬裕氏が実話怪談について語っているものだが、この中で夜馬氏は現在の実話怪談界の抱える問題としてこういうことを指摘している。
人気が高まって、演者も増えてくると、具体的な場所や、実際の事件を取り上げたりして、過激なことを言いたくなるものです。過去には、特定できる情報を掲載してしまい、出版差し止めになった本もありました。
私は活字の実話怪談を長年愛読しているが、語りの方は不案内な人間だ。ほぼ聞かない。夜馬氏の指摘は語りの世界についての比重が高いものだが、表現形態を問わず、実話怪談というジャンルそのものの持つ危うさについて踏み込んだものではないだろうか。松原氏の件も彼個人がどうこうという話ではなく、シーン全体の抱える構造的な問題に関わることだと思う。
この実話怪談にモヤモヤした
私も実話怪談を楽しんできたし、実在の事件に関する読み物記事等をやってきた人間だ。いうならば、所詮は同じ穴のムジナである。そういう自分からしても、読者として「さすがに、これはどうなのだろう……」と思った事例について、2つほど書いてみようと思う。
死者が多数出た実在の放火(偶然、火事の数日後に現場を通ったことがある)の疑いのある火災事件の通称を堂々とだして、怪異の大本である人物が放火の犯人ではないかという疑惑で終わる作品を読んだときは非常にモヤモヤした気分になった。2020年に発表された作品であり、出版社の企業リテラシーがさすがに気になった。本当に実話なら犯人を知っていて放置していることになるし、嘘なら嘘でひどい話だ。そもそも事件名ださなくても、何の問題もない話なのに。
また、モラルやリテラシーの話とは別に固有の名称の強度、実在の事件の強度に頼ったものは表現としてどうかという疑問もある。私の好きなタイプの実話怪談はそこで語られている背景が事実かどうか検証できなくても、怪談として独立した強度がある作品だ。