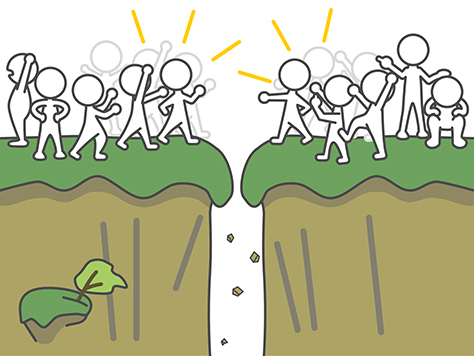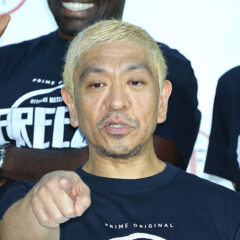PROFILE:
倉本圭造(くらもと・けいぞう)
1978年生まれ。京都大学経済学部卒業。マッキンゼー入社後、「グローバリズム」と「日本社会の現実」との矛盾に直面し、両者を相乗効果的関係に持ち込む新しい視座の必要性を痛感。その探求のため肉体労働現場やホストクラブにまで潜入し働く「社会の上から下まで全部見る」フィールドワークののち船井総研を経て独立。最新刊『論破という病 分断の時代の日本人の使命』(中公新書ラクレ)は、社会の「現場」と「インテリの議論」を繋ぐキャリアの集大成の1冊となっている。

ずっと昔から思っていること
――倉本さんは「メタ正義感覚」という概念を提示されていますが、その概念についてお教えいただけますか?
倉本 今の世の中って、問題が山積みなわりには、お手軽に「敵」を設定してSNSであいつはけしからん! って言い合ってるだけで、その問題は放置されっぱなしみたいなこと多いですよね。「メタ正義」というのはそういう状況を打破するための概念なんですね。
「メタに考える」というと神様視点から評論家的に話すようなイメージがありますけど、僕が言う「メタ正義感覚」というのはそうじゃなくて、むしろ「あらゆる人が持ってるベタな正義」をそのままほったらかしにしておかないで、その「ベタな正義」同士のぶつかりあいの中からどんどん「本質」に迫っていって、喧嘩ばっかりしてないでちゃんと問題解決に繋がる議論をしていこう…というコンセプトなんですね。
僕の著書の『論破という病』では、日常レベルの家族旅行の行き先を考える議論や、ビジネスでの議論、またはSNSでよくバトルになってる社会問題にいたるまで、どうやったら「ベタな正義同士のぶつかりあい」を「メタ正義」に転換する発展的な議論ができるかという話をお話しています。
――そういった考え方の原点は? 著書『論破という病』の中では、中学生の時は左翼を自称していたと書かれており、早くから「思想」にご興味があったことがうかがえますが。
倉本 中学に入ると、上級生には敬語とか、校則と教師の言うことは絶対みたいな風潮があって、そういった部分に対する反感が強いタイプの子どもだったんですね。それで学校で弁論大会があった時に、「学校という機関が、いかに社会の都合で人をデザインしようとしているのか。それに反抗して自分を守らなければいけない」みたいな、完全に場違いな演説をしたりしてました(笑)。
―― 中二病感ですね(笑)。