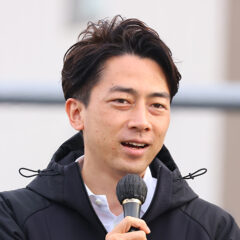たとえば元法政大学総長の田中優子は、事件の真偽ではなく、性被害を訴えた女性が公職を失ったという結果のみを抽出し、日本の構造的なジェンダー差別に変換。「性暴力を告発した女性が、議会と住民投票という公的な手続きによって失職させられた」「日本の政治の場における女性の地位の低さ、男性支配の構造が浮き彫りになった」と発し、暴走するツイフェミたちに権威のお墨付きを与えてしまったわけだ。
他にも「リコールは民主主義の衣を被ったリンチだ」とした著述家の湯山玲子、「被害者の記憶はトラウマによって混乱したり、不確かになったりすることがある」「それを理由に告発全体を虚偽だと決めつけるのはセカンドレイプだ」と新井をかばった精神科医の香山リカ、「たとえ性交渉があったとしても、町長と町議という圧倒的な権力差の中で起きたのであれば、それは性被害と見なされてもおかしくない」とした信州大学特任准教授の山口真由など、冤罪に加担した著名フェミニストたちは山ほどいた。
地方の一町長を標的としたネットリンチは、こうした発言が後押しする形で事実上“免罪”され、虚偽の告発があたかも既成事実のように拡散していったのだ。
事実よりイデオロギーの醜悪さ
ツイフェミたちの最大の罪は、自分たちの過失を決して認めようとしないことにある。事実、今回の判決で新井の嘘が認定された後ですら、その責任を一切取ろうとせず言い訳に終始している。沈黙を守っているのはまだマシな部類で、多くはデタラメな論理や論理のすり替えで自らが加担した冤罪から目を背け、道徳的優位性を保とうとしている。
たとえば北原は、判決後に出演したネット番組で、「告発が虚偽だとされたからといって、女性の声を疑ってはならない。私たちは彼女の勇気に寄り添っただけだ」と語り、noteや『週刊金曜日』でも「私はあの時の新井さんの状況を、まるで自分のことのように思ってしまう」「(新井氏の供述は)『虚偽』ではなく、ある種の『真実』と呼びたい」と主張。さらには、「私自身も、女性として日々性差別の被害にさらされている」と、自らを“被害者”の位置に置きはじめている。
「北原の発言は責任逃れと批判されましたが、本人に反省の様子はありません。同様に多くのツイフェミたちが判決を受け入れず、SNS上で『司法が間違っている』と言い続けています。彼女たちにとっては、事実よりも自分たちの掲げる“女性の声を信じろ”というスローガンを主張することのほうが重要なのでしょう」
また勝部も「事実に関係なく、草津町がリコールしたこと自体が問題だ」と、苦しい言い訳を繰り返し、主張を撤回していない。
「こうした態度こそ、ツイフェミたちの運動が被害者のためではなく、自分たちのイデオロギーを主張するためのものであることの証明でしょう。事実の検証よりも感情的な連帯を優先するのが典型的で、彼らにとって、男性からの権力的な性加害は常に真実であるというイデオロギーが絶対で、事実は二の次です」
本来は被害者支援を目的としているはずが、実際には事実の検証よりも「運動の勝利」を優先する姿勢が、社会の分断と冤罪を生む温床となっているのだ。