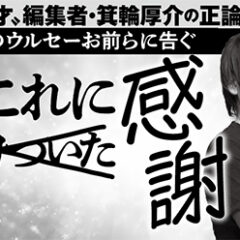参院選では多くの政党が猫も杓子も消費減税などバラマキ政策の主張に舵を切り、結果消費減税を主張する政党が躍進した。消費減税は一見ありがたい話だが、今の日本の状況において本当に可能なのか。米山隆一衆議院議員が解説する。※本稿は、5月16日発売『実話BUNKAタブー7月号』に掲載したものです。
減税コストは国民自身が負担
今、政界で、減税・給付・無償化が流行しています。国民民主党が「103万円の壁の引上げ(基礎控除の引上げ)」を打ち出して人気を博し、世論調査の支持率で野党第一党となって自民党に肉薄し、数々の地方選挙で好成績を収めたことが火をつけ、与党も野党も次々と、〇〇減税、〇〇給付、〇〇無償化を打ち出しています。その炎は参議院選挙が近づいたことでより一層燃え盛り、その勢いに慌てたのか慌てないのか、減税に慎重だと思われていた私の所属する立憲民主党までもが1年間限定の食料品消費税0%を打ち出して、政界はさながら減税・給付・無償化ブームの様相を呈しています。
もちろん、減税も給付も無償化も、それ自体が嬉しくない人はいません。皆さん結構誤解をされていますが、国会議員は通常の給与所得者で、私のように専門職だったり家業があったりして他からの収入がある者も含めて、ともかく全員、全国民と全く同じ税金、社会保険料を払っています。国会議員の年収は公表されている通り2187万8000円ともちろん大変な高額ですが、家族構成や控除等によって異なるものの、税・社会保障費で概ね収入の4割が徴収され、手取りは1200万円ほどです。
私は自分が1年に支払っている消費税額を正確に知りませんが、上記の手取り額からはざっと100万円程度と思われ、仮に消費税廃止で年間100万円(月8万円)が浮くなら、こんな嬉しいことはありません。これが食料品消費税0%だとしても、概ねこの1/5の年間20万円(月1万7000円程度)ほど浮くことになると思われるので、妻が料理好きで夫婦そろっておうちご飯が好きな我が家にとって、少なくない恩恵です。
しかし、ファイナンス(金融経済学)の世界でよく言われる通り、“There ain’t no such thing as a free lunch”、世にただ飯はありません。何せ日本は、油田を持って国家自体がお金を稼いでいるアラブの産油国でも、国有企業が世界中にエネルギーを売っているロシアのような国でもありません。日本の歳出のほぼ全ては国民の税金で賄われている以上、減税であれ、給付であれ、無償化であれ、実はそのコストは必ず私たち国民が負担をすることになります。
先程の消費税廃止を例にとって考えてみましょう。確かに消費税廃止は、恐縮ながら年収2000万円の私には、年100万円もの恩恵をもたらしてくれます。しかし、年収300万円の人は当然ながら最大で30万円、年収500万円の人でも最大で50万円しか恩恵はなく、その逆進性が問題だとされる消費税の廃止もまた、高所得者に有利な逆進的なものになります。
何より消費税を廃止したら、現在25兆円の消費税収がなくなるのですから、何らかの形でこれを補う必要が生じますが、これを、現在23兆円の税収の所得税の増税で賄うなら、所得税を倍増しなければいけません。