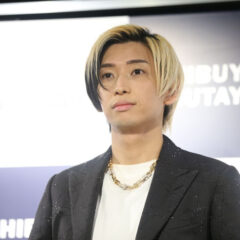そして、国の調査なり、ある程度の規制など法改正しなければ、このままだと来年以降もコメの生産量に関係なくこうした価格の変動や流通が不足するなどの問題が起きると話す。
「そもそも21万トンといえば、コメの年間生産量のわずか3%程度。なのにそれが消えただけでここまで値上がりするのはやっぱり流通に目詰まりや投機目的などがあるからだと思います。農水省が本腰入れて調べれば、行方不明になっているコメがどこにあるのか分かって、次の対策に行けると思うんですけどね」(同市場関係者)
現在のコメ騒動を受けて、江藤拓農相は参院予算委員会で、コメの販売事業者に国への届け出を義務付ける基準について、年間数量をいまの20トン以上から10トン以上に厳しく見直すと明言した。今回の反省からコメの流通状況を今後よりしっかり把握するためとしている。
前出の立憲民主党議員はこう話す。
「たしかに自由度は必要。だから規制はしなくてもいいかもしれないが、最低限コメがどこへどれだけ流れているかというせめて状況把握はしていかなければ、適正な指導などできない。それに、今回の騒動のようなケースだけではない。戦争が起きたり南海トラフのような大地震など有事の時にコメがどこへ行ったか分からないでは済まない。いまはスマホでどこどこの農家がどこの業者に売ったとか打ち込めばそれだけで済む話なので、記録を取ることに時間もかからない。中途半端に闇を残すのではなくて、コメの流通経路を“見える化”していくべきだ」
政治に翻弄されるコメ農家
コメの歴史を紐解くと、実は日本政府や政治家はコメを自分たちの外交などの交渉の道具として扱ってきた。このため、輸出入などが揺れに揺れ、生産者の農家などは振り回されてきた歴史がある。たとえば、こんな迷走気味の大きな流れがあった。
まずは1993年の関税貿易一般協定(GATT)ウルグアイ・ラウンドだ。
ここでは、日本は輸入米に高い関税を課す特例措置を適用する代わりに、通常よりも高い割増率での無税による最低輸入義務を負い、ミニマムアクセスとして年約77万トンを受け入れ、コメの部分的な輸入を解禁。 当時の細川護熙総理大臣は国民に対し「貿易立国として、世界経済の拡大と繁栄なくしてわが国経済の繁栄もないという強い信念のもとに交渉に臨んだ。将来にわたる国益を考えてコメの輸入という決断を行い、農業合意案を受け入れた」との談話を発表した。