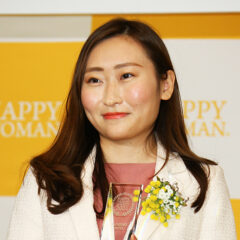いまさら言うまでもないことだが、日本で認可されている食品添加物は、いずれも国が厳格な検査を繰り返して安全性を保障したものだ。医学的根拠と科学的な数値が基準になっており、そこには古臭い左翼的な陰謀論が入り込む余地はない。もちろん問題があれば取り上げることはメディアの仕事だが、これらの基準を批判するのであれば医学的、科学的なエビデンスを揃えるべき。しかし批判記事は単純に、「こんな危ない物質は使うな。ゼロにしろ」と騒いでいるにすぎない。
それでも、週刊誌が食の安全に関して詐欺的な記事を出し続ける理由は単純だ。無知な読者にはこうした刺激的で恐怖心を煽る記事ほど読まれるからである。
一部の情弱な高齢者に向けた確信犯
実は以前からこうした食の安全に関する記事はメディアの間で鉄板のコンテンツとして知られており、定期的に話題を集めてきた。2000年代には左翼系雑誌『週刊金曜日』の特集記事をきっかけに話題を呼んだ書籍『買ってはいけない』がベストセラーとなっている。この『買ってはいけない』は一大ブームとなり様々なジャンルでシリーズ化したほどだ。また2018年には『週刊新潮』が「食べてはいけない『国産食品』実名リスト」なる特集を6号連続で掲載して反響を呼んだ。
もっとも、こうした「食の危険ブーム」は、そのたびに否定され、沈静化している。たとえば週刊新潮の「食べてはいけない国産食品実名リスト」の記事に関しては、あの『週刊文春』が真っ向から否定記事を書いて、完膚なきまでに論破している。「記事は食品安全委員会がとりまとめた食品健康影響評価を引用して添加物のハザード(危険因子)の特徴について紹介しました。ところが引用したのは評価書のごく一部で、結論部分を引用していないため結果として正しくありませんでした」とされている。
こうした過去があるにもかかわらず、週刊誌がまた同じような論調で食の危険性を喧伝しているのは、いかに確信犯でやっているかの証明だろう。
「いまやオヤジ系週刊誌はメインの読者層が年々高齢化しています。そんな読者にとって健康は最大の関心事ですからね。さらに言えば、いまだにこうした記事に影響を受けてしまうのは一部の情弱な高齢者や無知な若者だけ。フェイク情報でバカを騙して目先の読者を集めているようなものです」
いたずらに「食の危険性」を煽るメディアは、まるでフェイク情報という危険な添加物に手を出し、引き換えに自分たちの生命線である信頼性を失っているようなものである。
取材・文/小松立志
初出/実話BUNKA超タブー2024年11月号