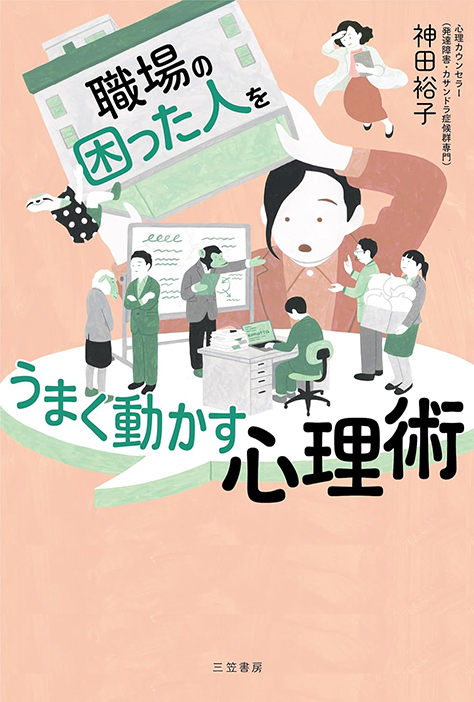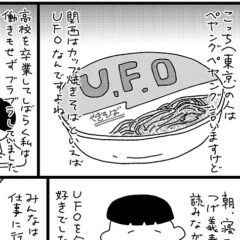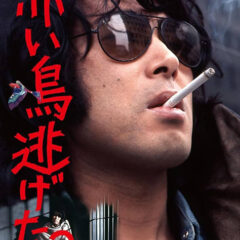困った人への対処方法を障害・疾患と結びつける
著者である神田氏がカウンセリングで実際に経験したことを中心に書かれているとは思うが、神田氏は医師でないので実際に発達障害を持つ人かどうかを判断できる立場にない。クライアントが神田氏に医師による診断名をつげなければ障害の有無を明言できないのだが、ここに取り上げられている人が全てそうであるのかは疑わしい。タイプ分けに障害・疾患名を使っただけにしかなっておらず、何となくそれっぽいというだけの話でしかない。そのこと自体が問題だが、本人及び出版社はよくわかってないようだ。
具体的に語られている困った人への対処方法は障害・疾患と結びつける必要がそもそもないのではないかというものが多い。例えば、お金で苦労したから人の手柄を横取りしてでも評価を得ようとする人をPTSD・発達性トラウマ障害タイプとしているのだが、根拠もよくわからないし、それを持ち出す意味も感じられず、そういうことをする人への接し方を提示すればいいだけでしかない。
対応の例としてあげられているものの中に内容自体が気になったところもある。知覚過敏が原因で入浴ができず異臭を放っているが注意しても改めない人への対応として、他の人と机を話すという対処方をとったことが書かれている。ASDタイプの項目で紹介されているが、この人がASD当事者だった場合、本人が納得しないままにこれをやると、大きな精神的な負担が余計にかかり、本人に別の問題が生じることになるのではないかという気がするし、「合理的配慮の提供」になっているか疑わしい。これはどうなのだろう。そもそも、その人が実際にASD当事者であるかすらもわからない。もっと説明がないと不安になる。
全体的には、忘れ物が多い人にはものの置き場を決めてあげる、スケジュール管理できない人は表を作ってチェックさせる、相手に共感を表明しながら話をする、心理的距離を取る、くどい話の打ち切り方、自分も困った人ではないかと顧みることが必要とか本当に普通のことと、各障害・疾患の薄い解説が少し書かれており、特筆すべきところが非常に見当たりにくい本だ。
・こだわり強めの過集中さん→ASD(自閉スペクトラム症)
・天真爛漫なひらめきダッシュさん
・愛情不足のかまってさん→ADHD(注意欠如・多動症)
・心に傷を抱えた敏感さん→トラウマ障害(PTSD、発達性トラウマ障害)
・変化に対応できない価値観迷子さん→世代ギャップ
・頑張りすぎて心が疲れたおやすみさん→疾患(自律神経失調症、更年期障害、うつ、適応性障害、不安障害など)
と六つのタイプ分けがされているのだが、障害・疾患と結び付けて書く必要は本当にない。それ無しでも成立するものばかりだ。