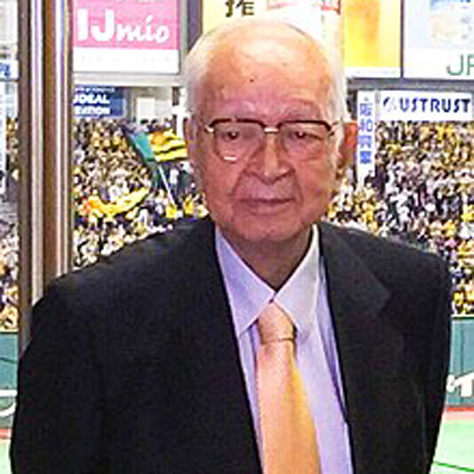東京大学哲学科に入学したわずか2カ月後に赤紙を受け取って軍に召集され、本土決戦を覚悟した陸軍近衛師団に配属される。
ほどなく終戦を迎え東大に復学したナベツネは、反戦の考えと天皇制への疑問から共産党に入党。同期には後に西武グループで台頭する堤清二もいた。
もっとも共産党での活動は2年ほどで、卒業前には共産主義に見切りをつけ、党からも除名処分を受けているのだが、この共産党での経験は後の独裁者・ナベツネに大きな影響を与えることになった。
「ナベツネは在学中に共産党内で目にした組織支配術を学び、後の読売グループ内での権力闘争や、メディア、政界といった巨大な集団をコントロールする独裁のベースになったと言われています」(政治評論家)
ナベツネは後に政界に絶大な人脈と影響力を手にして日本政治のフィクサーとして暗躍するようになるが、決して自分が政治家になろうとはしなかった。こうしたフィクサー志向の原点も、青春時代に体験した共産党での挫折と転向にあったと指摘されている。
「ナベツネが読売新聞の社説を書く〝主筆〟のポジションにこだわっていたのはよく知られていますが、1000万部という絶大な影響力のあるメディアで自分の政治的主張や思想を展開できる立場のほうが都合よかったのでしょう」(前出・政治評論家)
ナベツネは共産党を離れて以降、思想的に反共のスタンスを強め、冷戦期には反共を旗印とする自民系の保守政治家を擁護する一方で、社会党や共産党に批判的な立場を明確にしていく。
読売の紙面もナベツネが独裁者として牛耳るにつれ、それまでの中道だった論調からゴリゴリの保守支持となっていったのは紛れもない事実である。
例を挙げればキリがないのだが、たとえば読売新聞が自衛力の保持を明記した憲法改正試案を紙上で発表したことがあるように、憲法改正議論やアメリカとの安全保障政策でも読売は一貫して右的な立場を取り続けてきた。これもナベツネの仕掛けだが、日本最大のクオリティペーパーの主張が1人の独裁者によって支配されていたという事実を考えると空恐ろしくなる。
政治権力とのズブズブの癒着
メディア人としてのナベツネの足跡を見るだけでも、そのヤバさがよくわかる。読売新聞の政治部記者となったナベツネは、新人時代から自民党の大物政治家に食い込むことで社内でも出世していく。権力とズブズブになることが出世につながるという状況は、まさに現在の新聞メディアが抱える問題そのものとも言えるだろう。