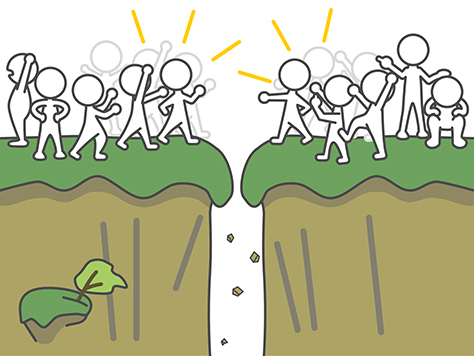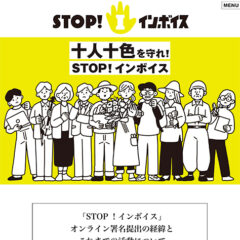倉本 そうですね。インテリの世界で生きてきたから、インテリ世界の合理性というのは十分わかるんですが、それが現場寄りの細部のところでちゃんと配慮の行き届いたものにできるかどうかで、全然結果が変わってくるんですよね。その後、今は中小企業向けのコンサルタントになってて、10年で150万円ぐらい平均給与を上げられた例もあるんですが、それが成功したのは「インテリの考える合理性」と「現場レベルの細部の事情やお気持ち」とちゃんと双方向的な「メタ正義」を破壊しないように配慮してきたからなんですよ。
一方で、いわゆる「アメリカ型」に社会運営すると、「インテリがヤンキーの気持ちを全然理解しない」方向に振り切れちゃうんで、果てしなく分断が進んじゃうんですよね。
――トランプの勝利は、有権者が感じる、エリートやリベラル派に対する反発が大きかったという分析もありますね。
倉本 副大統領のJ・D・ヴァンスの『ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち』にも、エリートが何気なく「良いこと」と考えてる施策が、細部では現場に合ってなくて労働者階級の人々の気持ちをチマチマと傷つけ続けていることに対する違和感を強い怒りを持って書いてますね。そういう「理想の押し付け」だけが横行すると社会が病んじゃうので、理想と現実を双方向に繋ぐ丁寧な「メタ正義」の議論が必要なんですね。
党派的な極論にも意味がある
――『論破という病』では、「再開発問題」「電力問題」「外国人との共生」「歴史認識問題」と、ケーススタディを基に「メタ正義」の実現への筋道が提示されていますね。
倉本 例えば「外国人との共生」でいえば、「外国人が増えて治安が悪くなってる!」と言う人に対して、「ファクトチェックすれば犯罪率はほとんど増えていない!」と返しても、あまり意味がない。
――保守にしてもリベラルにしても、外野で無責任に焚き付けている人は別にして、実際に外国人と共生する中で治安の低下を感じている、いわゆる「体感治安の悪化」を感じている人も当然いますね。