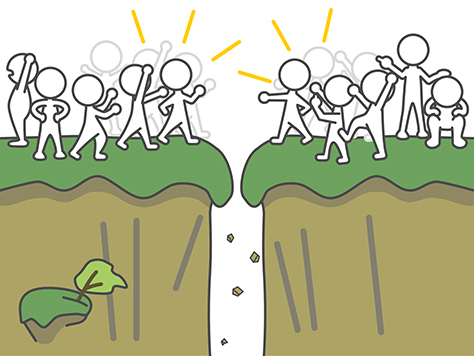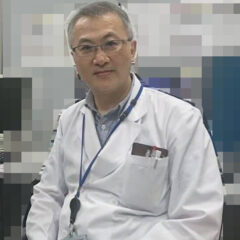倉本 でもそれ以来、「あいつは優等生だけど、俺たちの気持ちを分かってくれる」みたいに、ヤンキーからも一目置かれるようになって。
――ヤンキーにも共通する「反抗のマインド」を言語化したというか。
倉本 その経験は大きかったかもしれません。なんか「正しいインテリ」と「それに馴染めない反抗者」に分断されちゃうと社会が病んでくるなと思ってて、そこの間に「双方向に」やりとりが生まれるようにならなきゃいけないとは、ずっと昔から思ってることですね。僕が京大の卒業後に外資コンサルのマッキンゼーに入って、それを辞めたあとホストクラブや物流関係の肉体労働やらをしてた時期があるのも、そういう思いからですね。
――またカルト宗教にも潜入されるなど、いわゆる超グローバルエリートコースから、もっと日本的で生々しい世界に入られたそうですね。
倉本 フィードワーク的な意識もあったし、本当にメンタルが弱ってたんですよ。 マッキンゼーや外資コンサル、 要するにアメリカ的なものには、「エリートとそれ以外」を分断するような、「 俺たちは考える側/ お前らは言うことをきく側」 みたいな思想があるんですよね。 それに対する違和感が大きすぎて自分も精神的に病んでしまった。そこで「もっと現実社会のリアルを知らなくちゃいけない」とメチャクチャ青臭いことを感じて、そういう世界に飛び込んだんですね。
エリートやリベラル派への反発
――ある種のショック療法ですね。倉本さんは著書の中で、合理的なものを「水の世界」、 人間のつながりを重視するものを「油の世界」という概念でお話されていますが、 マッキンゼーは究極の水の世界、 ホストや宗教などは究極の油の世界ですね。その両方を見たと。