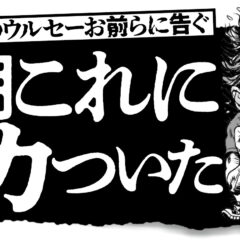また近年は法規制も強化されている。17年の改正FIT法で事前認定制度が導入され、22年には「盛土規制法」が施行。地盤調査や環境アセスメントを経なければ事業許可は下りず、自治体が議会レベルでストップをかけた例もある。つまり「やりたい放題の乱開発」は制度的に封じられており、批判派が好んで語るような無法地帯など存在しないのだ。
「開発側も莫大な投資をする事業者である以上、環境アセスメントを無視するほど愚かではないし、自治体も無謀な案件にはゴーサインは出しません。実際に伊東市では市議会が計画を否決し、大船渡でも住民の意見を踏まえて事業が中止されています。制度が機能しているからこそ計画がストップする事例もあるんです」(前同)
太陽光は再エネ発電の優等生
CO2排出など環境負荷の側面からも太陽光発電は優秀だ。たとえば火力発電1kWhあたりのCO2の排出量は石炭火力で約820g、天然ガス火力でも約490gに上る。対して太陽光は約40g前後と一桁違う。しかもこれは製造・輸送を含めたライフサイクル全体の数字で、稼働後はほぼゼロ排出になる。
原子力は確かに低炭素だが、廃炉や廃棄物処理のコストを考えれば「安い電源」とは到底言えないうえ、福島第一原発事故で証明されたように取り返しのつかないリスクを抱えている。一方の太陽光は稼働すれば基本的に二酸化炭素も放射性廃棄物も出さない。太陽光ばかりを「環境破壊」と呼ぶのはあまりにバランス感覚を欠いている。
他の再生可能エネルギーと比べても利点は大きい。風力発電は立地制約が大きくバードストライクや騒音問題もある。洋上風力の建設コストは太陽光の倍以上とされ、波力・地熱はまだ実証段階で普及には時間がかかる。
「結局、日本の地理条件を踏まえれば太陽光をメインに一部を風力でまかなうという方向性がもっとも現実的な選択肢なんです」(環境ジャーナリスト)
また、「太陽光では電力を安定供給できない」という批判も的外れだ。確かに太陽光は昼間しか発電できず、曇天や雨天では出力が落ちる。だがこれは再エネ全般に言える性質であり、蓄電技術や分散型電源との組み合わせで十分に対応できる。
「気象庁の統計を見ても、日本の平均日照時間は全国平均で年間約1900時間と世界的に見ても長く、地域ごとの気候条件を勘案すれば、一定の発電量を安定して確保できる地点は多い。風力発電や波力発電のほうがむしろ不安定要素が大きいことは専門家が繰り返し指摘しています。不安定だから役に立たないという批判は、最新の技術とコストの実態を知らない人の意見です」(前同)