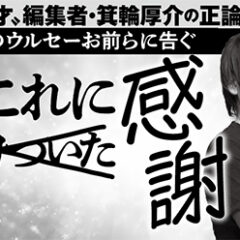事実を捻じ曲げ「太陽光パネルは悪」の大合唱
このところネット上でメガソーラー建設を批判する声が急増している。引き金となったのは2024年末から25年にかけて地方紙や全国紙の地域面で相次いで報じられたメガソーラー計画をめぐる住民の反対運動だ。
具体的には釧路市の湿原地帯で計画されていたメガソーラー建設や、静岡県伊東市での山林伐採を伴う設置計画、さらには岩手県大船渡市での太陽光発電所構想などが遡上に上げられ、「太陽光発電=環境破壊」という図式が声高に叫ばれている。
釧路の案件は、湿原近くに大規模な太陽光発電施設を建設するというもの。しかし建設地が湿地の保全を目的としたラムサール条約登録地の周辺ということで、反対派が「世界に誇る自然を破壊する暴挙だ」と声を上げ、議論が拡大した。地元紙には「タンチョウヅルの生息地が脅かされる」などのコメントが並び、SNS上では「釧路湿原がパネルで埋め尽くされる」といった極端なイメージ画像が拡散された。
伊東市の計画では、山林を切り開いてメガソーラーを設置する構想が持ち上がっていたが、「大雨のたびに土砂崩れを起こす危険がある」「観光資源である景観が台無しになる」と反対の声が上がり、議会は住民の声を受けて最終的に計画を否決している。
大船渡の事例では、港湾近くの丘陵地を利用した太陽光発電所の計画が、「津波被害を受けた土地を悪用するな」「漁業者の生活が脅かされる」といった声により、最終的に事業者が撤退する結果となっている。
各地の事例がニュースとして報じられるたび、ネットでは「自然破壊の偽善エコ」「やっぱり太陽光はインチキ」といった言葉が飛び交っているが、彼らの主張はおおむね以下のような意見に集約される。 「自然を破壊してエコを語るな」 「太陽光発電は安定した電力供給には向いていない」 「外資に土地を売り渡し、外国製パネルを使用するのは安全保障上も大問題だ」 「メガソーラー建設は補助金目当ての利権ビジネスだ」
確かに一見するともっともな意見にも思える。こうしたニュースが出るたびに、もはや日本全国でメガソーラーパネル建設が暴走しているかのようですらある。
だが、本当にそうなのか。