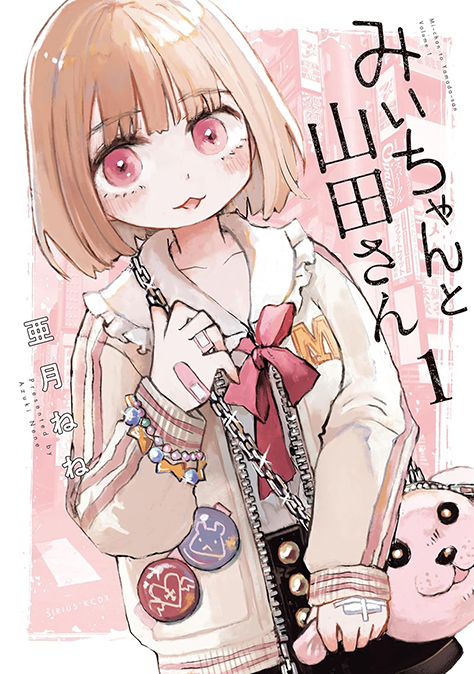一種の「ポルノ」として消費されている側面が強い
コミックス3巻では『ケーキの切れない非行少年たち』の著者・宮口幸治と亜月の対談が掲載されている(このセッティングにも、なんらかのエクスキューズを感じ、モヤモヤするのだが)。
そこに、「みいちゃん」を気にかけており、彼女の母親に特別支援学級に入れることを提案するも激しく拒絶される小学校時代の担任教諭について、宮口が親との信頼関係をもっと形成しておかないといけなかったという専門的な知見を示すところがある。
しかし、実際のところ彼女は「みいちゃん」の母や祖母の拒絶、特には母(彼女は実兄との間に「みいちゃん」を産んでおり、彼女自身も軽度知的障害あるのではないかと読者がおもえるように描かれている)のエキセントリックな反応を引き出すためのガジェットとしての役割しかないわけで、そういった指摘も意味がないような気分になってしまった。
本作を真鍋昌平の作品と比較することもできるが、それよりも本作にテイストが似ているのは中村敦彦のノンフィクションだろう。
企画AV女優を扱った『名前のない女たち』シリーズ、10年代の東京で貧困を理由に性産業に従事する女性を扱った『東京貧困女子。』、『ルポ中年童貞』といった中村の著作は、取材対象者のネガティヴな面を強調する傾向があり、一種の「ポルノ」として消費されている側面が強いが、『みいちゃんと山田さん』も多くの人にそういった消費の仕方がされているように感じるし、作者や編集部がどう考えているのかはっきりとしたことは言えないが、「エクスプロイテーション」作品として機能している側面があることは否定できないのではないか。
社会的問題に対して、問題の本質について自覚的に取り組み、かなり勉強しているであろう岡田索雲の『ザ・バックラッシャー』も単純にみじめなアンフェおじさんを馬鹿にして楽しむような消費のされかたもしてしまうわけで、そういうものだと言われればそういうものなのだが……。
「みいちゃん」というキャラクターが過剰に盛り込まれ過ぎている一方で、同僚の発達障害の女性(彼女に関しても明確に発達障害であるという言葉は使われていない)のエピソードや「山田さん」の「毒親」エピソードは解像度が高いというか過剰になり過ぎておらず、作者の実体験や周囲のエピソードが反映されている部分ではないかと思う。また、客の男性の不快なエピソードも過剰になりすぎないリアリティを保っている。
前述の「日刊SPA!」の記事で亜月は10年代の夜職の独特な雰囲気を再現したかったと語っているが、そういった部分はちゃんと反映されているのではないだろうか。