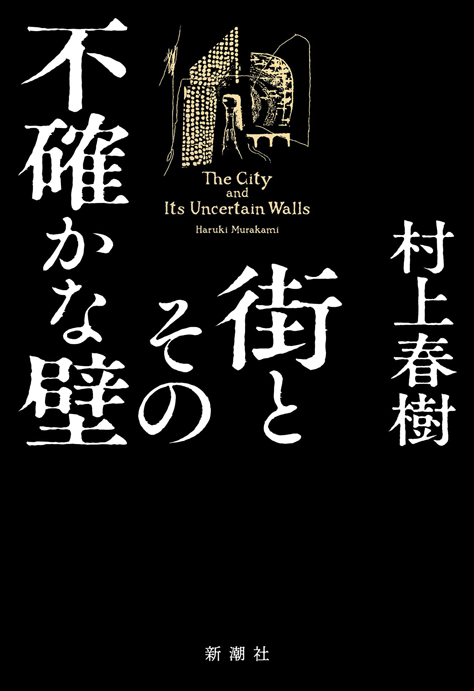繰り返される空虚な祭り
本誌が発売されるころには、にわかハルキストたちやワイドショーなどのテレビ番組が村上春樹の4年ぶりの長編小説『騎士団長殺し』を手に大騒ぎを繰り広げ、春樹フィーバーが巻き起こっているに違いない。もしかすると、本誌読者のなかにもこのビッグウェーブに乗り、『騎士団長殺し』を買ってしまった流されやすい人がいるかもしれない。
最初にはっきり言っておくが、村上春樹を読んで喜んでいるのは、単なるミーハーか、モテないオヤジか、キモオタか、メンヘラ文系女子のどれかだ。
たしかに、村上春樹の新作というのは、とりわけ長編小説の場合、発売そのものが一大イベントとなる。
実際、2009年に発売された『1Q84』や13年の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』では、各地の書店でカウントダウンイベントが行われ、当日の午前0時から販売が開始されるなど、まさにお祭り騒ぎとなった。そして、このにわかファンが大騒ぎする様子をワイドショーなどのテレビが大々的に取り上げるというのがいつものパターンなのだ。
もちろん、今回の新作でもまったく同じ構図が繰り広げられている。『騎士団長殺し』は発売前から計30万部の重版が決まり、すでに累計120万部。街中のカフェではいち早く村上春樹の新作を入手したにわかファンがドヤ顔で本を広げ、各職場も村上春樹の話題一色になっているはずだ。しかし、この空気に負けて『騎士団長殺し』を読むのは、●●●(←汚物の名前が入ります)を食べるのが流行っているからといって自分も●●●を食べてみるようなもの。4年ぶりの長編小説だろうがなんだろうがそんなのはにわかハルキストにまかせておけばいいのである。
作られたブームと100万部
そもそも、現在の村上春樹人気は、大手の出版社が仕掛けて作り出したインチキなブームにすぎない。
じつは、2000年代までの村上春樹はサブカル好きに人気が高いだけの「普通の売れている作家」だった。日本文学というのは基本的に家族の葛藤や貧乏話をベースにした辛気くさいものが多い。それにくらべて、春樹作品はアメリカの現代文学をオマージュした比喩を多用し、文脈にはジャズやロック、アートが散りばめられるなど非常におしゃれ。しかも、謎解きやエロ要素もある。そのため、従来の純文学を読まない人たちにもウケたわけだ。