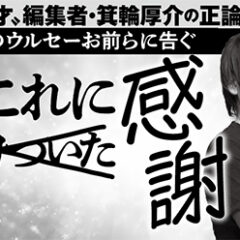「努力しても報われず、少なくない税金を払っているのに、ちょっと文句を言えば貧困層から『まだ余裕があるだろ』と扱われる。彼らにしてみれば『では、お前らはどれだけ社会に貢献しているのか?』と言いたくなるのも無理はありません。その意味では『富裕層とそれ以外』だけではなく、
低所得者層と中間層の間にも分断が生まれ始めているんです」(前出・政治評論家)
今回の参院選は、声が大きいだけのバカな低所得者層によって日本の政治が引きずられはじめていることを、ハッキリ可視化したということなのだ。
低所得者は本当に貧しいのか
そもそも、低所得者層は本当に生活が苦しいのか。
低所得や貧困の定義は様々だが、一般的に生活保護や福祉給付など、行政上の支援対象になりやすい低所得ラインとしては、年収120万円未満が「貧困ライン(相対的貧困)」とされ、年収150〜200万円未満が低所得者層となる。
「年収300万円に届かない世帯は『準中間層』とされますが、これは言い換えれば『準貧困層』でもあります。2022年の平均世帯年収は約524万円ですが、より現実的な中央値で見ると約405万円。現実のサラリーマン層の多くはこの400万円前後に集中しており、これが中間層になりますね」(経済評論家)
では、低所得者層は中間層に比べてどれだけ優遇されているのか。ここでは何かと話題になる生活保護受給者を例に比較してみよう。ちなみに生活保護の要件としての年収上限は法律に明記されておらず、その代わりに、「世帯の収入が、その世帯に必要な最低生活費を下回っている」かどうかで判断される。令和6年度の「世帯に必要な最低生活費」は、東京在住の単身者で13.6万円。夫婦世帯で19〜22万円。母子家庭で17〜20万円となっている。
令和6年時点での生活保護受給者は、全国で約204万人になる。地域差はあるものの、彼らは単身者でも最大で月約13万円+最大5万円以上の住宅補助を受けられる。医療費は実質ゼロ、NHK受信料も免除、上下水道料金の減額制度や交通機関の割引もある。つまり、現金+家賃+医療+ライフラインのすべてをまかなえる20万円近い価値が保証されているのだ。